2025年11月にAmazonがトータルサポートメンバーを務める「東京2025デフリンピック」が開催されます。日本で初めてのデフリンピックは、聴覚障がいを持つ選手たちが21の競技に参加する国際大会です。バレーボール選手として4大会連続出場した元デフリンピアンである、Amazon社員の猪野康隆さんに、デフリンピックの意義と見どころを教えてもらいました。
デフリンピックは、4年に1度、開催される「きこえない・きこえにくい人のためのオリンピック」
東京2025デフリンピック(正式名称:第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025)は、約80の国や地域から、約3000人もの選手が集まる聴覚障がい者のためのオリンピックです。
開催期間は、2025年11月15日から26日までの12日間。21種の競技が東京都を中心に、静岡県、福島県でも実施されます。デフリンピックとはどのような大会なのか、どのように競技が行われるのかを猪野さんに教えてもらいました。
静かな会場で迫力満点の試合が観戦できるデフリンピック
Q1. デフリンピックはどのような大会ですか? いつ始まったのですか?
猪野さん:デフリンピックは、英語で「耳が聞こえない」という意味の「デフ(deaf)]」と「オリンピック」を組み合わせた大会名で、「きこえない・きこえにくい人のためのオリンピック」です。夏季大会と冬季大会がそれぞれ4年に1度、開催されています。「国際ろう者スポーツ委員会(ICSD)」が主催し、世界で活躍するデフアスリートが数多く参加します。
デフリンピックの第1回大会は、1924年にフランスのパリで開催されました。日本でデフリンピックが開催されるのは初めてです。東京2025デフリンピックは、100周年の記念大会になります。
Q2. デフリンピックには、どのような競技がありますか?
猪野さん:東京2025デフリンピックでは、陸上、バドミントン、バスケットボール、ビーチバレーボール、ボウリング、自転車(ロード・MTBマウンテンバイク)、サッカー、ゴルフ、ハンドボール、柔道、空手、オリエンテーリング、射撃、水泳、卓球、テコンドー、テニス、バレーボール、レスリング(フリースタイル・グレコローマン)の21競技が行われます。
Q3. デフリンピックの参加資格はどのようなものですか?
猪野さん:2つの資格が必要です。1つは、耳の聞く力を補う補聴器などを外した状態で、聞こえる一番小さな音が55デシベルを超えていること。55デシベルは、普通の声での会話が聞こえないレベルです。もう1つは、各国のろう者スポーツ協会に登録し、デフスポーツ団体ごとに行われる選考競技会で、記録や順位などの出場条件を満たしていることです。
Q4. デフリンピックとパラリンピックは何が違うのですか?
猪野さん:パラリンピックには、体が不自由だったり、視覚に障がいがあったり、さまざまな障がいのあるアスリートが出場しています。そのため、それぞれの競技には、障がいの種類や程度を補うルールがあります。聴覚のみの障がいを持つアスリートは、ほかの障がいに比べ、身体能力が高いことから、パラリンピックへの出場が認められていません。そこで、聴覚障がいのあるアスリートのための大会としてデフリンピックが開催されています。デフリンピックの各競技のルールは、オリンピックとほぼ同じです。
Q5. デフリンピックは、オリンピックとで、競技の進め方が違いますか?
猪野さん:デフリンピックの競技中は、補聴器など、聴力をサポートする器具を身につけることはできません。そこで、国際手話(世界共通の手話)などのほか、視覚で試合の進行がわかる工夫があります。
例えば、100m走などのトラック競技では、ピカッと光るフラッシュランプでスタートを知らせます。フラッシュランプは、バスケットボールやハンドボールなど、ほかの競技でも活用されます。また、サッカーやラグビーなどでは、審判は笛を鳴らすと共に、旗や手を上げて、選手に知らせます。

Q6. 手話で作戦会議をしたら、相手チームにわかってしまいませんか?
猪野さん:手話は言語によって異なるので、国際試合の場合はわからないことが多いです。
Q7. デフリンピックでは、どのように応援したらいいですか?
猪野さん:ぜひ会場に足を運んで、観戦し、選手を応援してください。試合は、事前申し込みの必要がなく、誰でも無料で観戦できます。デフリンピックの会場は、選手たちや監督が手話でコミュニケーションをとるので、たくさんの人がいるのに、静かなことに驚くと思います。そして、世界トップレベルのデフリンピアンが競い合うので、オリンピックと同様の迫力があります。まずは、試合の面白さを楽しんでほしいです。

そして、選手たちを応援するときは、手を使って、目でわかるサインを送ってください。東京2025デフリンピックでは、「サインエール」という新しい応援スタイルが作られました。聴覚障がい者の身体感覚と日本の手話をもとに作られた応援のための手話です。サインエールは、音声を使わずに会場全体の一体感を生み出す、素晴らしい応援文化です。すべての人がデフアスリートに想いをたくさん届けることができます。
デフリンピックに4回連続出場した猪野さんが思い描く「共に歩み寄る社会」
猪野さんはバレーボール選手として、1997年のコペンハーゲン大会から2009年の台北大会まで4回連続で、デフリンピックに出場しました。その経験から、どのようなことを学んだのでしょう。また引退後は、デフアスリートを支援する活動を積極的に行っています。そして今は、Amazon社員として、聴覚障がいを持つ社員をサポートしたり、社内外にデフリンピックを広く知ってもらうための活動にも力を入れたりしています。そんな猪野さんの日々の様子も聞いてみました。
Q8. 猪野さんのAmazonでのお仕事を教えていただけますか?
猪野さん:私は、2016年からAmazonスタジオで、商品撮影に関わる業務を担当しています。最初は人事部の仕事に応募しましたが、大学でデザインを学んだ経験が生かせるようにと面接段階でスタジオでの仕事を紹介されました。現在は、撮影商品の入出荷の管理、機材のセッティングなどの撮影準備、スタジオの運営まで、撮影が効率よくスムーズに進むように、一貫したサポートを行っています。
Q9. なぜバレーボール選手としてデフリンピックに参加するようになったのですか?
猪野さん:クラブ活動ではバスケットボールをしていたのですが、20歳のとき、大学のバレーボール部の主将が私の潜在能力の高さを評価してくれて、「デフリンピックを目指してみないか」と誘ってくれたのが、きっかけです。私は体が細かったので、体がぶつかり合うバスケットではすぐに倒されてしまい活躍できていなかったこと、そして当時はまだ、デフリンピックの種目にバスケットボールはありませんでしたので、デフリンピック出場という夢をバレーボールで追いかけることにしました。社会人になってからは、地域の聴覚障がい者のバレーボールチームや健聴者のクラブチームと掛け持ちしたりしながら、2009年の引退までプレーしました。

デフリンピックには、1997年(コペンハーゲン)、2001年(ローマ)、2005年(メルンボルン)、2009年(台北)に出場しました。2000年に台北で開催されたローマ大会の予選会(アジア太平洋ろう者スポーツ大会)では優勝しましたし、2008年のアルゼンチンで開かれた「デフバレーワールドチャンピオンシップ」で3位に入賞できたことは、忘れられない思い出です。

今は、Amazonのバレーボールクラブに所属して、同僚たちとプレーを楽しんでいます。
Q10. デフリンピックでは、どんなことを学ばれましたか?
猪野さん:世界レベルの競技に挑戦し続けることで、努力の先に待つ達成感やチームメイトとの絆の深さを実感できました。技術面はもちろん、精神面でも大きく成長できたと思います。デフリンピックは、単なる国際スポーツ大会ではありません。帰国後に私は、デフリンピックは、世界中の聴覚障がい者が「自分らしく生きる勇気」を分かち合い、「違いは弱みではなく、強みなのだ」ということを確認し合う場であること、そして「聞こえないことは、私の個性であり、特別な能力なのだ」と確信を持って言えるようになりました。
世界のアスリートと言語や文化の壁を越え、スポーツを通じた深い絆が育まれます。また、自分を誇らしく思える経験をしたことは、私の人生の大きな財産になっています。私を支えてくれた方たちには深く感謝していますし、デフリンピックの素晴らしさを、もっと広く、多くの人に伝えていきたいという原動力になっています。

Q11. デフリンピックに参加するためのサポートはどうだったのでしょうか?
猪野さん:デフリンピックは、オリンピックやパラリンピックに比べ、知名度が低く、選手の多くは苦労しながら競技を続けています。私も働きながら、選手を続けるのは大変でした。スポンサーが見つかりにくいので、練習や遠征にかかる費用は自己負担になります。強化合宿や試合に参加するためには休暇の日数が足りないこともありました。東京2025デフリンピックをきっかけに、支援の輪が広がることを期待しています。
Q12. 東京2025デフリンピックには、Amazonもトータルサポートメンバーとして参加しています。猪野さんも参加されている、障がいのある方とその支援者のためのAmazon社員による有志グループ「PWD(People With Disabilities)Japan」が中心になって活動していますが、どのような支援をしているのでしょうか?
猪野さん:2023年の秋、私が東京でデフリンピックが開かれることを知り、PWDに相談のメールを送ったのが始まりでした。デフリンピックの認知度がとても低いことや選手の経済的困窮などをプレゼンテーションの形にまとめ、送りました。仕事とは関係のない内容ですし、たった1人の社員の相談を受け止めてくれるか不安でした。でも、勇気を出して送ってみたら、すぐに返答があり、うれしかったです。

Q13. Amazonは東京2025デフリンピックに、どのような支援をするのでしょうか?
猪野さん:デフリンピックのトータルサポートメンバーとして大会への協賛を行うほか、Amazon Payを活用した大会への募金活動と「ほしいものリスト」を活用したAmazon「みんなで応援」プログラムでの大会関係団体への物品支援などを行っています。そうしたAmazonの強みを生かした包括的な支援で「選手が競技に専念できる環境作り」と「大会の認知度向上」に取り組んでいます。社内に向けても、応援メッセージの動画配信やボランティア参加者の募集、デフアスリートの講演会などを実施しています。
Q14. 猪野さんは、PWDメンバーとして、聴覚障がいを持つ社員が働きやすい環境作りにも積極的に関わってきました。どのような取り組みをしてきたのでしょうか?
猪野さん:聴覚障がい者は、目でのコミュニケーションが重要になります。そこで、翻訳ソフトを導入して、ミーティングでの情報アクセスを改善したり、Amazonスタジオでビジネス手話ビデオを定期配信するようにしたりしました。
なかでも印象に残っているのは、Amazonの社内で通路やドア付近で起こる衝突事故を防止する「お知らせライト」の導入です。スチール製のドアに人感センサーのランプを設置し、ドアの向こう側に人がいると点滅して知らせてくれる仕組みを同僚と3人で提案しました。このアイデアは、2020年のGlobal Accessibility Awareness Month(GAAM)※期間中に日本のPWDで行われた企画で賞をいただきました。「お知らせライト」はAmazonのFC(フルフィルメントセンター)などに設置され、活用されています。
※GAAMとは、Amazonでアクセシビリティについて考える月間で、毎年5月にさまざまなイベントなどが開催されます。
Q15. 聴覚障がいを持つ方も暮らしやすい社会を作るため、どのようなことが必要と感じていますか?
猪野さん:生まれながらに聞こえない私は、聞こえる人たちがうらやましく、「なぜ自分だけが」と、絶望に打ちのめされることもありました。でも、成長するなかで、聞こえないことを自覚し、人と違うことを受け入れようと思えるようになりました。「私がどんなに努力しても健聴者とまったく同じことはできないように、私と同じ人生を歩める人もこの世にはいない」と気づいたのです。そして、聴覚障がい者が健聴者と同じになるのではなく、お互いに歩み寄る方向を目指すことに希望を感じるようになりました。

夢や希望は簡単に手に入るものではありません。それは、デフリンピックへの挑戦で教えられたことです。困難に打ち勝ってこそ、夢や希望はつかめます。そのために、本当にやりたいと思ったら、絶対にあきらめてはいけない。私は、どんな仕事にも本気で挑戦し、全身全霊で取り組んでいます。私の真剣すぎる姿は、端から見ると滑稽かもしれません。でも、それでいいのです。99人が理解してくれなくても、たった1人が理解し、歩み寄ってくれるだけで、うれしいことなのです。もし、今、悩んでいる人、とくに子どもさんがいたら、「いろいろな人に出会うことをあきらめないで、頑張ってほしい」と伝えたいです。たくさんの人とコミュニケーションをとるなかで、きっと光が見えてくると思うからです。
デフリンピックをきっかけに聴覚障がいをもっと知りたいと思ったら、手話を覚えたり、相手の目を見てゆっくり話したり、アクションを起こしてほしいです。すべての人がお互いに理解し合える社会を築いていくことが、私の夢です。
Q16. 最後にAmazonを手話で表現していただけますか?
猪野さん:手話でAmazonを表すときは、一文字ずつ表すこともできますが、次の順序でAmazonのロゴにあるスマイルマークを描きます。動きや視覚的なイメージを用いることも手話の特徴です。
①「a」の指文字を作ります(Goodの形から横にする)
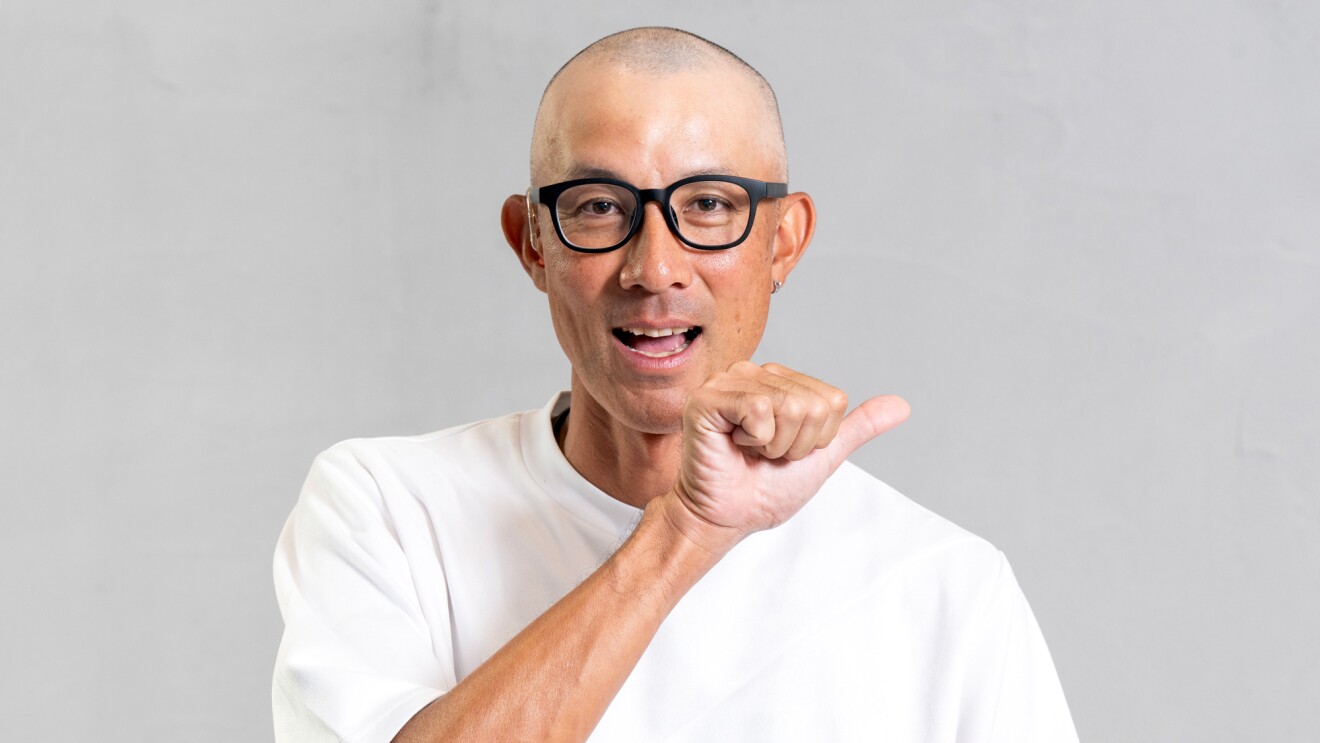
② 作った「a」の指文字の手で、Amazonのロゴにある特徴的なスマイルマークを表現します
左から右へ、上がりながら曲線を描くように動かします(Amazonのロゴの矢印が「A」から「Z」まで伸びている様子を表現)
Amazon Payを活用した大会への募金活動について詳しくはこちら
Amazon「みんなで応援」プログラムでの大会関係団体への物品支援について詳しくはこちら
東京2025デフリンピック 公式サイトはこちら











