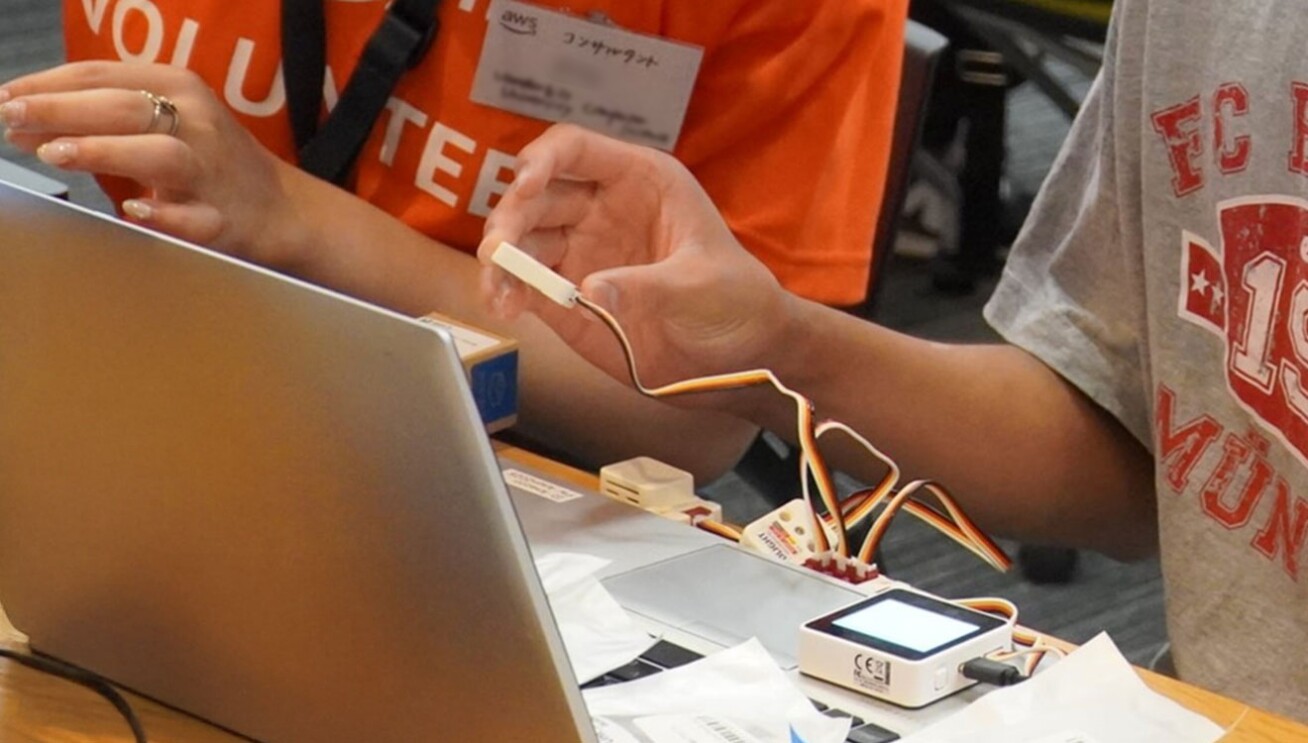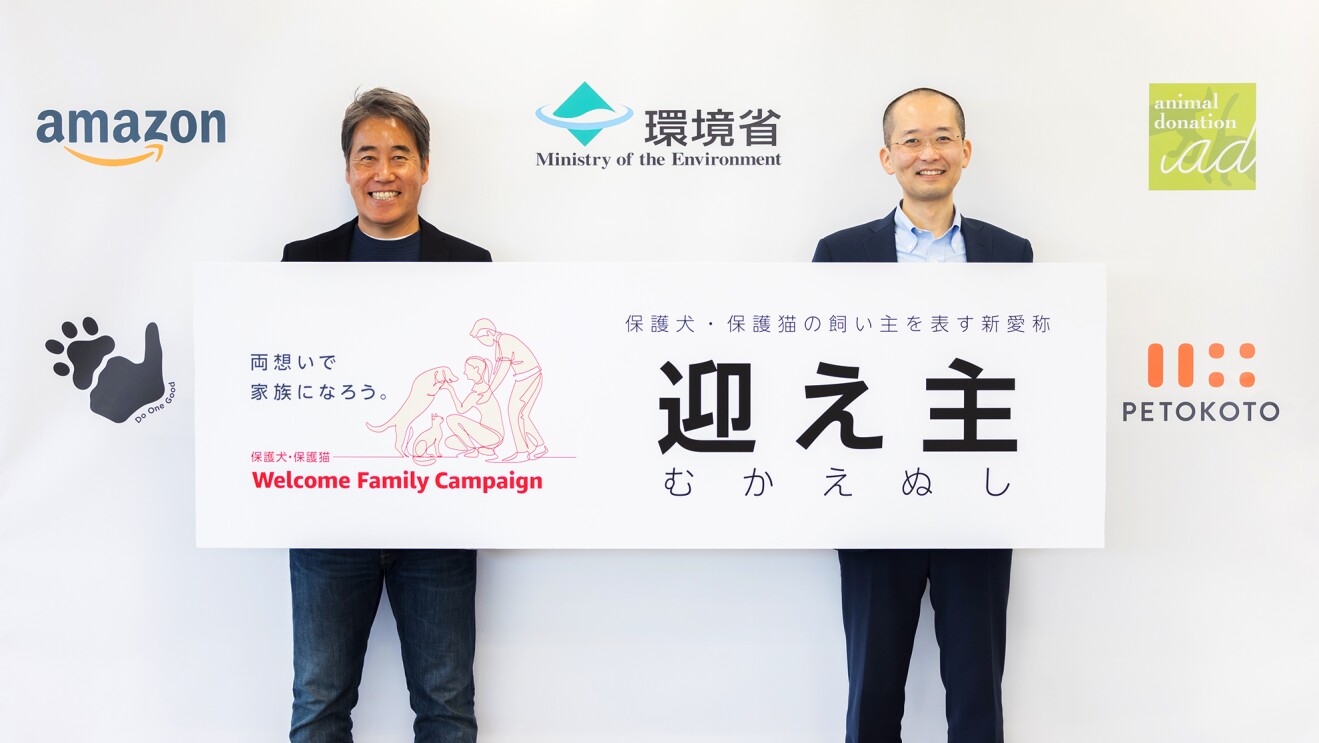ゴールが見えていれば、必ず壁は乗り越えていけると思います
Team MC2
三菱電機株式会社先端技術総合研究所 主席研究員 堂前幸康さん
中京大学工学部長 教授 橋本 学さん
中部大学工学部 ロボット理工学科 教授 藤吉弘亘さん
中京大学工学部長 教授 橋本 学さん
中部大学工学部 ロボット理工学科 教授 藤吉弘亘さん
掃除機のようなモーター音を響かせながら、ロボットの腕がゆっくりと近づき、A4サイズのリングファイルを吸い上げようとする。しかし持ち上がるのは表紙だけで、リングファイルはパタパタとはためいて、元の箱に落ちた。
7月27日から30日の3日間、名古屋で開催されたロボットコンテスト、アマゾン・ロボティクス・チャレンジ(ARC)で何度も目にした光景だ。今年で3回目となったARCに参加したのは、応募のあった約30のチームから選抜された日本、アメリカ、オーストラリア、ドイツ、インド、イスラエル、オランダ、シンガポール、スペイン、台湾の大学や企業からなる16のチーム。
コンテストの競技種目は、単純に言えば、「商品を棚に入れる」「商品を棚から出して箱に入れる」の2つの作業だが、形、大きさ、重さ、色、素材が異なる商品に、多くのチームは苦戦を強いられた。
「一般の方からすると、ロボットが物を持ち上げて棚に入れるなんて、簡単だろうと思われるかもしれません。サイエンス・フィクションに描かれている自由自在に動くロボットのイメージがありますから。でも現実的にはまだまだ課題が多いんです」とARCに3回連続で参加しているTeam MC2のリーダー三菱電機の堂前幸康さんは語る。
ARCの競技である「棚入れタスク」と、「棚出しタスク」は、Amazonの物流拠点で行われている作業から着想を得たものだが、ロボットにその作業を実行させるためには、商品を適切な方法で持ち上げるための機械的な技術に加え、商品を識別する画像認識やロボットが自分で学習するディープラーニングなどのソフトウエアの開発力も要求される。

「その競技内容を見て、まさに我々の強みをいかして解くべき課題だと思った」と話すのは、Team MC2のメンバーの1人、中部大学の藤吉弘亘教授だ。彼の研究室が得意とするディープラーニングによる画像認識技術と、中京大学の橋本学教授の研究室が得意とする3次元物体認識技術、そして三菱電機の産業用ロボットとセンサー技術を用いてこの課題を克服すれば、産業用ロボットの新たな活路を見出せるのではないかと3人で意気投合しチームを発足させたという。
三菱電機の先端技術総合研究所は兵庫県、中京大学と中部大学は愛知県内に所在する。今回ARCに参加するにあたり、遠隔地でも共同研究が進められるよう、全体構想とロボットシステムの制作を三菱電機が担当し、中京大学と中部大学がソフトウエアを共同開発。そしてそのソフトウエアの改良とロボットとの調整を三菱電機が行うという手順をとった。
ソフトウエアの仕様は、機械やセンサーなど各分野からの制約があり複雑だった。学生たちは、互いの研究室を行き来しながらデータの取得や、ミーティングを重ね、企業のプロフェッショナルたちの期待に応えるべくシステム開発を進めた。
橋本教授は、「ディープラーニングのような中核となる技術はもちろん大切ですが、それを上手に動かす工夫のような小さな技術も重要なため、それを要所に散りばめることに注意を払った」と言う。
そして最終調整に入ると、学生たちも兵庫県まで出向き、三菱電機の社員たちと共に何日もかけて調整を行い、チーム一丸となって大会に臨んだ。

その努力の甲斐あり、大会初日の「棚入れタスク」では、棚に見立てた箱にロボットが次々と商品を納め、見事3位に入賞。しかし2日目の「棚出しタスク」では、指定された商品のほとんどが、偶然にも他の商品の背後に配置されていたという不運に見舞われ、制限時間以内に商品を取り出すことができず、僅差で決勝ラウンドへは進めなかった。
橋本教授に学生たちの様子を尋ねると、「落胆したとは思いますが、3位に入賞できたことで自信がついたと思います。この会場にやってくると、自分たち以外にも世界中に同じ課題に取り組んできた学生たちがたくさんいる。それを目の当たりにすることができる機会を提供できるのは工学教育にとって大きなメリットです」と笑顔を見せた。
藤吉教授は、「ARCの良いところは、参加したチームが、ロボットの国際会議に併設するワークショップでARCの取り組みについての発表を行い、研究交流を行っていることです。お互いがどんなことを実践したのか、競技では見ることができなかった各チームの取り組みを後から知ることができるため、研究者のコミュニティ全体の技術力を底上げする機会となっています。今後もロボットコミュニティの発展に貢献したい」と語る。

ロボット開発にはまだたくさんの壁があると言う堂前さんに、その壁をどう乗り越えるのかと尋ねると、少し考えてから次のように語った。
「人々が期待している自在に動くロボットに少しずつ近づいていると信じて、ロボットを着実につくり、研究開発を続けていくことです。ゴールが見えていれば、必ず壁は乗り越えていけると思います。少子高齢化が進み労働力不足が懸念される日本では、人を助けるロボットやロボットシステムがこれからもっと必要になるはずです。そのための努力をこれからも愚直に続けていきたいです」